つみたてNISAを始めたいと考えている方へ。
2024年から制度が進化し、「新NISA(つみたて投資枠)」としてさらに使いやすくなっています。 非課税期間が無期限になり、長期的な資産形成に最適です。
投資は難しそうに思えても、少額から気軽に始められます。本記事では、初心者が安心して始めるためのポイントを解説します。
始めると変わる3つの安心ポイント
結論から伝えると、新NISAは「投資は怖い」と感じる人でも安心して始められます。預金より増えやすく、税金もゼロ。さらに、少額から始められるので、初心者でも無理なく続けられます。
預金より資産形成を進めやすい
銀行預金は金利がほぼゼロ。資産形成が進みません。
新NISAなら、世界中の株式や債券に分散投資できます。長期的な成長が期待できるのが魅力です。
たとえばS&P500などの主要株価指数は、長期的に年平均5〜10%程度成長してきました。預金との差は歴然です。
もちろん元本割れのリスクはあります。ただし、新NISAは分散と長期運用で資産形成を目指しやすい仕組みです。
非課税メリットで将来の不安が軽くなる
新NISAは投資の利益が非課税です。通常は約20%(正確には20.315%)の税金がかかりますが、この制度ならゼロ。運用成果をそのまま再投資でき、複利効果が強く働きます。
さらに2024年の新制度では非課税期間が無期限になりました。 旧制度は20年間の期限がありましたが、新NISAならずっと非課税のまま保有できます。
たとえば同じ銘柄でも、20年後に数十万円から100万円以上の差が出るケースも。税金を気にせず積立を続けられるため、心理的なハードルも下がります。
老後や教育資金といった将来への不安を和らげる大きな武器です。
少額からコツコツ始められる
新NISAは月100円から積立OK。大きな資金は不要です。生活に無理のない範囲で始められます。
少額積立は「ドルコスト平均法」を自然に活用できます。毎月一定額を投資することで、価格が高いときは少なく、安いときは多く購入。平均購入単価が抑えられ、リスク分散につながります。
投資額は自分でコントロール可能。家計に合わせて調整すれば、将来の不安を減らしながら着実に資産形成できます。
初心者がつまずく3つの壁と解決法

投資初心者が抱える不安は、多くが情報不足や思い込みです。よくある3つの壁と、そのシンプルな解決法を紹介します。
壁1「仕組みが難しそう」→ 実は3ステップで完了
新NISAは実はシンプルです。
- 証券会社で口座開設
- 毎月の積立額を設定
- 投資信託を選ぶ
これだけ。あとは自動で買付が進みます。
「銀行口座に毎月自動でお金を預ける」のと同じ感覚。設定したら放置でOKです。専門知識は不要。基本の流れを一度押さえれば安心してスタートできます。
壁2「どの証券会社を選ぶ?」→ ポイント連携で決める
初心者に人気なのは楽天証券とSBI証券。どちらも低コストで使いやすいです。
楽天証券
- 楽天ポイントが貯まる・使える
- 楽天カードユーザーにおすすめ
SBI証券
- 取り扱い本数が業界最大級
- Vポイントが使える
結論:普段使っているポイントで選べばOK。難しく考えず、続けやすさを優先しましょう。
壁3「銘柄を選べない」→ 王道インデックスから始める
最初から完璧な銘柄選びは不要です。
王道のインデックス型投資信託を選べば、世界中の株式に分散投資できます。リスクを抑えながら安定運用が期待できます。
おすすめ銘柄
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- S&P500連動型ファンド
長期で積立を続けるなら、これで十分。「正解を探す」より「続けやすさ」を優先しましょう。
リスクはゼロではないが長期積立で安心
新NISAは投資なので、元本割れのリスクはあります。でも「長期積立」で不安を和らげられます。
価格の上下に一喜一憂せず、コツコツ続ければ相場の変動が平均化されます。
過去の株式市場を見ても、短期的には下落があっても10年、20年単位では成長してきました。長く続けるほど価格変動の影響を受けにくくなります。
時間を味方につければ、不安を抑えて資産形成できます。
最初の一歩を踏み出す3ステップ

新NISAを始める手順はシンプル。「口座開設」「積立額の設定」「銘柄選びと自動積立」の3ステップです。順番に実践すれば、初心者でも迷いません。
証券口座を開設する(スマホで最短1日)
新NISA口座を開設しましょう。手続きはオンラインで完結。スマホから最短1日で開設できます。
必要なもの:
- 本人確認書類
- マイナンバー
楽天証券やSBI証券なら、口座開設の流れがシンプル。アプリで進捗確認もできます。
銀行口座を開くのと同じくらい手軽。実際には数分の入力と書類提出で済みます。
毎月の積立額を決める(無理なく続けられる金額)
無理のない積立額を設定しましょう。
つみたて投資枠の年間上限は120万円(月10万円相当)。でも上限いっぱいに積み立てる必要はありません。まずは月1万円や2万円から始めるのがおすすめです。
参考:新NISAの投資枠(最大活用した場合)
- つみたて投資枠:年120万円
- 成長投資枠:年240万円
- 合計:年360万円
大切なポイント
- 余剰資金で投資する
- 生活費や緊急資金とは分ける
- 慣れたらボーナス時に増額も可
続けやすさを優先することが、長期投資の成功につながります。
おすすめ銘柄を選んで自動積立を設定
積立額が決まったら、銘柄を選びます。
初心者におすすめ
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- S&P500連動型ファンド
どちらも低コストで長期投資向き。多くの利用者から支持されています。
銘柄を選んだら、証券会社のアプリで自動積立を設定。毎月一定日に自動で買い付けが行われます。タイミングを考える必要なし。
自動化すれば「気づいたら投資が進んでいた」状態に。迷いや不安を最小限に抑え、安心して続けられます。

長く続けるための3つのコツ

新NISAの効果を最大化するには、続ける仕組みが大切です。下落時も積立継続、シミュレーションで将来像を確認、定期的な目標の見直し。この3つでブレずに長期投資を続けられます。
相場が下がっても積立を止めない
初心者がやりがちな失敗:相場が下がったときに積立を止めてしまうこと。
でも実は、下落時こそチャンス。同じ金額でより多くの口数を購入できます。
積立を続ければ平均購入単価が下がり、回復局面で利益を得やすくなります。これが「ドルコスト平均法」の効果です。
短期的な損益に振り回されず、仕組みに任せて積立継続。これが成果につながります。
増え方をシミュレーションして安心感を得る
投資を続けるには、将来の資産額を具体的にイメージすることが大切です。
証券会社や金融庁のシミュレーションツールで簡単に試算できます。毎月の積立額と想定利回りを入力するだけ。
シミュレーション例
月2万円を年率5%で20年間積立 → 元本480万円が約820万円に
数字で可視化すると「続ければここまで増える」という実感が得られます。相場変動にも動じない気持ちを支えてくれます。
- 新NISAは預金より効率的に資産を増やせる
- 利益が非課税、非課税期間は無期限(2024年の新制度)
- 月100円から始められ、無理なく継続可能
- よくある壁にはシンプルな解決策がある
- 長期でコツコツ続ければ、相場変動にも動じない
定期的に振り返って目標を再確認する
新NISAは長期投資が前提。でも定期的な振り返りも大切です。
資産形成の目的は人それぞれ。教育資金、老後資金、住宅購入など。生活環境が変われば、目標や積立額の調整が必要になることも。
おすすめの振り返り頻度 半年〜1年に一度
証券会社アプリで運用実績をグラフ表示。変化を視覚的に把握できます。
無理に増額する必要なし。余裕があれば増額、厳しければ一時減額もOK。柔軟に対応することが継続のコツです。
最初の一歩
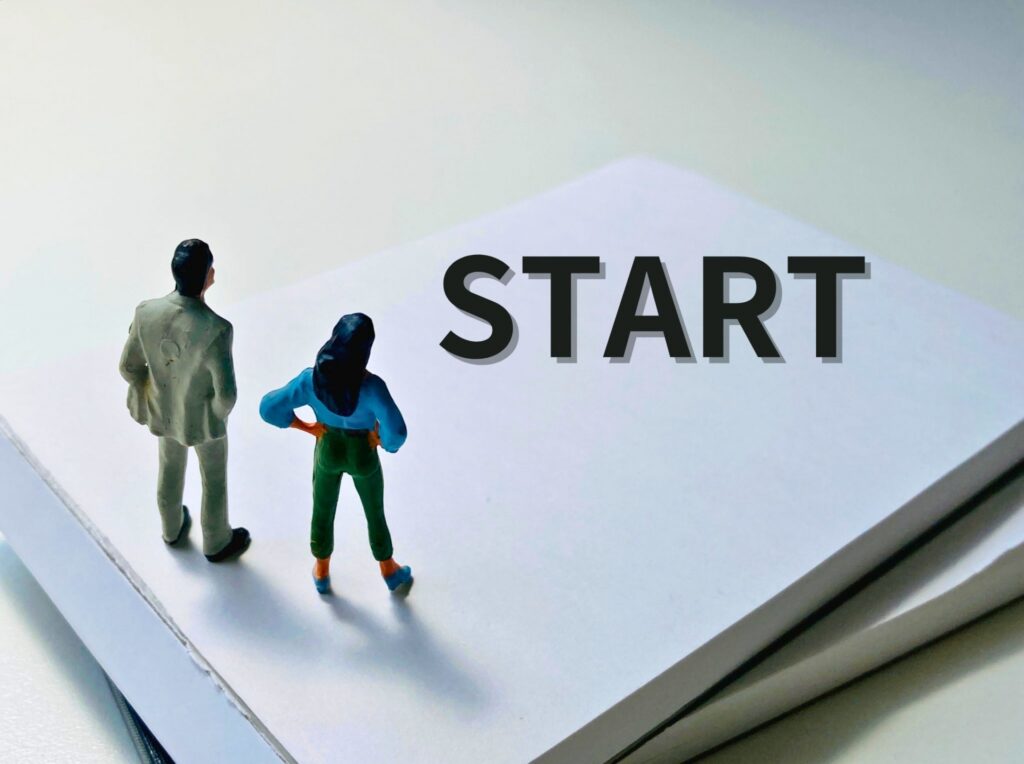
投資に不安を感じる人でも、新NISAなら小さな一歩を踏み出せます。今日から準備を始めて、未来の安心を積み立てましょう。
金融庁の公式シミュレーションで将来の資産額を試算
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/tsumitate-simulator/
証券会社の口座申込ページを確認







コメント